 |
 |
 |
八幡神社前で、左手から来る国道56号線と合流して直進する。
この日は、とても寒く向かい風の強風で、時々雨の悪コンデション。
めげずに、56号線のゆるい坂道を下り続け、民宿「よしもと」を過ぎたあたりから上り坂となる。 |
 |
 |
 |
坂を越えて、下り坂となり「平山」バス停前を通り、その先で上り坂、次に下りとアップダウンを繰り返し、
「八百板峠」バス停前を通る。
それにしても、向風の強風にほどほど参り、菅笠が飛ばされないように必死に握りしめる。
右側に休憩所。 |
 |
 |
 |
ゆるい坂を上り切ったところに、カラフルな「オレンジロード」看板と「接待木・ のなる木」案内板(合成写真)。 のなる木」案内板(合成写真)。
(要約):この花壇に植えてある「愛南ゴールド」は、歩き遍路さんが、水分・栄養補給をし疲れを癒してもらえるように、
ボランティア(お遍路)さんによって植えられ、管理されている。歩き遍路のみなさん、どうぞご自由にお食べ下さい。
愛南ゴールドは、品種を河内晩柑といい愛南本町が生産量日本一を誇っている柑橘です
一つの重さにつき約40%ほどの果汁があり、ほどよい酸味の効いた日本版グレープフルーツのような味わいが特徴。
愛南ゴールドの食べごろは4月から6月。
ということで、残念ながら季節が1月ではご好意に甘えることができませんでした。
愛称「オレンジロード」の56号線を進み、その先にあるのは、伊予ミカンでしょう。
坂の頂上付近にも、愛南ゴールド花壇。 |
 |
 |
 |
坂を下り、「菊川」バス停前を通り、右手下方に自動車がことこと走るのどかな田園風景。
「この先歩道がなくなりますので、ここでお渡りください」交通標識で、左側に横断して進む。 |
 |
 |
 |
左側屋敷内に、「御荘町天然記念物 御荘室手の大南天」石柱上にメガネ学者風猫(合成写真)。こんな猫、見たことない!
56号線の坂道を、延々と下り続けて海岸線に近づいて進む。
「外室手」バス停を過ぎた左側に、「足摺宇和海岸国立公園」看板。下方に美しい入江。 |
 |
 |
 |
長い下り坂の右側に、何やら建築途中の建物見たいなもの。これって、内海展望所。
そこから展望できる景色は、多分これ。
相変わらずどこへ行っても向かい風の強風。 |
 |
 |
 |
坂の途中に、花壇。でも、ここには、愛南ゴールドは植えていないみたい。間違ったらごめんなさい。
さらに下り、左手下方に柏崎漁港。
左に大きくカーブし、橋を渡った先の柏郵便局前信号のところで、56号線を横断する。
この横断歩道地点が、観自在寺から10.2km。
インターネットで、この郵便局に地元中学生が作成した「柏坂へんろ道マップパンフレット」が置いてあると聞いていたので、
尋ねると、「今は、置いてない。そこに掲示されているだけ。」と、応対した若い女性の局員。
イラストと写真入りで作成した、新聞紙2ページ大の「遍路道MAP」と「へんろMAP」が掲示されていました。 |
 |
 |
 |
56号線を横断して柏川沿いに進み、丁字路角に順に「平城へ2里三十四丁」、「四国のみち」、「龍光寺 」の新旧の道標。 」の新旧の道標。
四国のみち道標には、「柏坂休憩地2.3km」表示。
正面の山の頂上に、白い風力発電。風の強いところなんですね。 |
 |
 |
 |
交差点は、橋を渡らず直進し柏川沿いに進む。
すぐ左側に、可愛い「おせったい はなばたけ 柏小学校」案内板。
今日は季節でなく見れなかったが、後ろの空き地一面に美しい花が咲くんですね! ありがとう、みんなで仲良く育ててね。 |
 |
 |
 |
ポールの道標ワッペン(合成写真)に従い左折し、民家前を申し訳なく通り、
突当りの「柏坂」道標(合成写真)から右折して階段を上る。
時は、10:04。 |
 |
 |
 |
坂道、枯葉道、そして「沖の黒潮荒れよとまゝよ 船は港を唄で出る 野口雨情」句碑。
これからも、雨情のいろいろな句碑が現れる。
野口雨情が、昭和12年ころこの内海村を訪れしばらく滞在した縁のよう。 |
 |
 |
 |
石畳道、谷間道。ベンチと「柏坂休憩地 1.2km」道標。
「柏坂休憩地」道標が、次々と立っているが実はどこが休憩地なのか、現地にその標識が見つからず、ついにわからなかった。 |
 |
 |
 |
| すぐ先左側に、ベンチ。そしてベンチ、またベンチ。 |
 |
 |
 |
| ベンチ。 ネェー、崖道の左側のこの岩、爬虫類に似ていません? 「トイレまで100m」案内標識。 |
 |
 |
 |
現地でも分かり難いが、分かれ道は左手を上り、小さな広場に柏を育てる会の「柳水」案内板とベンチ。
柳水(要約):この地に弘法大師が立寄ったとき、往還の旅人の渇きを癒すため柳の杖を突きたてたところ、
甘露の水が出てきたので柳水と呼ぶようになった。
その杖が根付いて一本の柳が代々代々育っている。
さて、その柳とはどこに?
左手上方に休憩所。もしかして、この休憩所が、「柏坂休憩所」?と思うが、証拠なし。
この地点は、標高400m。時は、10:56。観自在寺から、約3時間30分。 柏坂上り口から、約1時間。 |
 |
 |
 |
休憩所右わき奥に、柳水大師。(休憩所まで行かないと、分かりません)。
元の道に戻り山道を上り、右下に先ほど案内のトイレ。さらに上り続け、ここにもベンチ。 |
 |
 |
 |
柏坂峠の最高標高470mを過ぎ、山道を下り、下り切った突当りに明り。
舗装道路を横断し、「柏坂へんろ道」道標の立つ坂道を上り、林道に入る。 |
 |
 |
 |
「トイレまで100m」案内標識、コーナーに内海村商工会青年部製「癒し椅子」。
ベンチと椅子を使い分けているつもりはありませんが。言われたままです。念のため。
枯葉を踏んで林道を進む。 |
 |
 |
 |
左側に、「岩松村土居儀平築営」石柱と石積。こんなところの石積って、何のためだろう?
先ほどの案内標識のトイレ、そしてベンチ。 |
 |
 |
 |
愛南町と宇和島市の境界を過ぎた辺りに、分かれ道。
左手の坂を下り、右側に清水大師と「大師水」案内板。
大師水(要約):ある年の夏、この地に一人の巡礼娘がのどの渇きで意識を失い倒れていたところ、
弘法大師が現れ、娘に「傍らにある、シキミの木の根元を掘るように」と言って姿を消した。
意識を取り戻した娘が、シキミの根元を掘り起こしたら清水が湧きだし、娘がその清水を飲むと持病の労咳も治ったという。
案内板前を通り、突当りの右の山道を上る。 |
 |
 |
 |
かろうじてわかる山道、上り切って先ほどの道と合流して左折する。
合流点に「← 茶堂休憩地 2.6km」四国のみち道標。
坂道の途中、両側に「ゴメンん木戸」と呼ばれる2個の石が立てられている。
ゴメン木戸(要約):明治の頃、この辺りは放牧が行われ、牛が逃げないように近くのヒヤガ森山頂まで延々と石畳を築かれていた。そのとき、ここに木戸が設けられていて、人びとは「ゴメンナシ」と言って通行した。 |
 |
 |
 |
少し下った左側に、標高460.1m水準点。
標高470m地点から随分下がってきたと思ったが、たった10mですか? へんろみち地図は、間違いないですよね?
尾根道を下り、左側に「接待松(別称ねぜりまつ)跡}案内板。
接待松(要約):ある日、病気で足の不自由な人が箱車に乗り、大綱をかけ引っ張り上げてもらっていた。
この地にさしかかった時、俄に一陣のつむじ風が吹き荒れ、曲がりくねった大松が箱車を押し潰すかのように思われ、
思わず箱車から逃げ出そうとした。そのはずみで、長年の足の病が治ったという。
また、地元の人達がこの場所で、お遍路さんに茶菓子の接待をしたが、
名物となっていた大松は、昭和30年頃に伐採され、今は朽ちた株を残すだけとなった。
案内板脇のきれいなべべ着たお地蔵さんの後ろに、朽ちた切株。多分これが接待松跡。
なお、案内板下の赤い→は、「WCまで220m」。 |
 |
 |
 |
ここにも、「癒しの椅子」。
視界の開けた草むら道を直進する。
なお、ここで草むらの右手を下ると、消毒されたトイレが4戸(イベントの名残?)。 |
 |
 |
 |
ここから、何故か急に道幅が狭くなる。ここにもベンチ。
草むらの中に、「猪のヌタ場」案内板。
猪のヌタ場(要約):猪が水溜りの中の泥で水浴びをしさらに傍らの木に体をこすりつけ、
付着している寄生虫を殺し毛づくろいをするところをヌタ場という。ここに、ヌタ場があった。 |
 |
 |
 |
「牛の背」と呼ばれる尾根道。
細い坂道を下り続け、「女兵さん 思案の石」案内板。
女兵さん 思案の石:食料難の時代、かつぎ屋の兵次郎さん──女のような姿態をしていたので、人呼んで「女兵さん」──
ヤミ物資をかつぎここ迄来ると、不意に雲をつくような大入道が現れ「コラッ女、こっちえ来い」
「わたしゃ、男なんですよ」「ナラ証拠を見せい。わしのより立派やったら、コラエテやらい」
腰を抜かさんばかりの兵さん、やおらニッコリ、褌に手をかけました。兵さんをからかったつもりの大入道、
一物をチラッと見、あわてて退散しながら「上には上があるのお、わしゃたまげた」
これからもこのような話が出てくるが、
これらは「トッポ話(ほら吹き話)」といい、愛媛県南予地方の津島町で語り継がれている。
さらに下り、左側に「思案坂」標識。案内板がないので、意味不明。
|
 |
 |
 |
えぐられた坂道の右側に、「狸の尾曲り」案内板。
狸の尾曲り:昭和61年秋、「四国のみち」の調査に来た、県の係官3名、この街道のはえぬきの案内にしたがい、
峠から下りる途中雑草茂るこの地で、道を誤って反対側に入り、しかも逆に100メートルばかり上った。
若い係官「オッチャン、さっき通った所に出たんじゃない。木の皮を削っているよ」
ハッとした案内人「アリャ古狸め、またワルサしおって」
皆さん、ここで、ご同伴が、美人やハンサムに見えなかったら「ソレワ大ごと」──気いつけなはれや
細い道は、しばらく苔むした岩になり滑りやすく恐るおそる下り続ける。
左側に、「鼻欠けオウマの墓」案内板。
鼻欠けオウマの墓:明治の初め、梅毒にかかり、鼻がなくなったオウマさん。女性自身をしゃもじでたたきながら、
くり返していました。「お前の癖が悪いから、わしゃ鼻落ちた」
若い頃の面影もないオウマさんを、里人たちは大事にいたわり、死後「婦人病除け」に、参拝された時期もあったそうです
ただ、墓がどこにあるかわかりませんでした。 |
 |
 |
 |
右側に「クミヒチ屋敷 由来」案内板。
クミヒチ屋敷:むかし、ここにひなびた館があり、オクメさん、おヒチさんの美人姉妹が住んでいて、
近在の男達が、米一握り水人桶持参し、遊びに来ていました。
やがて、玉のような男子が生まれ、「クメヒチ」と名付けられ大切に育てられましたが、
姉妹は当時流行した悪性のオコリにかかり、二人ともアッいう間に亡くなりました。
成人したクミヒチさんは、ここに一庵を建て二人の霊を祀ったそすです。
ただ、周囲にはそれらしき墓は見当たりませんでした。
その先で、広い道に出て右折し、道なりに左にカーブし、へんろ道道標(合成写真)の立つ分かれ道は左手の坂道を下る。 |
 |
 |
 |
林道を下り、「馬の背駄馬」の痩せた尾根道を進み、続いて「馬の背」尾根道を進む。
駄馬は、悲しい。 |
 |
 |
 |
下り続け、下り切った突当りの「へんろ道」道標(合成写真)の立つ丁字路を、右折する。
ここの「へんろ道」道標は、「HENRO MITI」ローマ字併記。外国人は、助かると思います。
ここには、左手に茶道休憩所。
休憩所に掲示されている、「トッポ話」。
土佐の愚か村話の名人が、津島町の茂八と、トッポ話の試合に来ました。
名人が茂八を訪ねると、家の前で10歳あまりの女の子が遊んでおり、「茂八さんはおるかの」と聞くと、留守だといいます
「どこへ行ったのか」と尋ねると「父やんは裏の山がかやりよる(くずれている)いうので、線香持ってつっぱりに行ったぞなし」と答えます。土佐の名人、さすが茂八の娘と感心して「お母やんは…」と聞くと、
「母やんは座敷で、のみにぽんし(ちゃんちゃんこ)を着せて遊ばしよる」といいます。
名人はこれではとうてい茂八にかなわぬとばかり、ほうほうのていで逃げ帰ったとか。 |
 |
 |
 |
そして茶道休憩所の裏に、黄色トイレ。
丁字路に戻り、坂道を下り、左にカーブして木々の間の細い道を進む。
両側の木々を見ると、最近切ったばかりの小枝があちこち。
道にはみ出していた小枝を、旅人の邪魔にならないよう切っていただいているのでしょう。細かいご配慮、感謝申し上げます |
 |
 |
 |
坂を下り切って舗装道を斜めに横断し、峠入口から初めての民家の前に出る。
この舗装道の地点が、観自在寺から16.0km。時は、12:58。柳水大師から、約2時間。
松尾峠と柏坂峠を越えて来て
(愛媛県側の)松尾峠は、安全対策として防護柵も完備したよく整備された快適な道に対し
柏坂峠は、むしろ自然を残した山道で、
休憩所やトイレを多く設置し(宇和島市津島地区)トッポ話で楽しませて旅人の癒しを与える、こんなようにも思える。
同じ愛媛県の山でありながら何がそう違わせているのかと、考えてしまう。
民家の前を通り、人の気配の感じられない道を進む。
右側高台に、茶堂大師。 |
 |
 |
 |
| 廃屋の前を通り、道は段々細くなり、ついには完全に山道、足場の悪い道を下り続ける。 |
 |
 |
 |
三本松大橋(大橋と言っても、せいぜい長さ4~5m)を渡り、左折して竹林の道を下る。
左崖下斜面に、巨大なシイタケ栽培場。 |
 |
 |
 |
| 道の右側にも、シイタケ栽培場。視界が開け、芳原川沿いに進み左折して小祝中橋を渡って、右折する。 |
 |
 |
 |
| 舗装道を道なりに進み、集落に入り、短い集落を通り過ぎ畑道を進む。 |
 |
 |
 |
次の集落を出て、その先で橋を渡って左折して進む。
柏坂峠を上ってから初めて見る、自動車。
畑道を通り、次に芳原川沿いに進み清酒泰山前を通る。 |
 |
 |
 |
| しばらく芳原川沿いに進み、分かれ道は右手の坂を下り、46号線トンネルを潜って突当りを右折し、再度芳原川沿いに進む。 |
 |
 |
 |
芳原川にかかる高岡橋を渡り、右折して道なりに進む。
「お遍路さん休憩所(トイレ)あります 800m先」標識。残念ながら、見つけることができませんでした。 |
 |
 |
 |
| 平坦な道を淡々と進み、また芳原川に接近して進み、その先で右折し芳原川にかかる金剛橋を渡る。 |
 |
 |
 |
橋を渡り終えたらすぐ左折し、川原沿いの細い舗装道を進む。
多分春の天気の良い日などは、この道は絶好のハイキングコースになると思う。
珍しい名前の於泥橋袂を直進し芳原川沿いを進む。 |
 |
 |
 |
川沿いの真っ直ぐな道、ただこのとき道路工事中で途中「立入禁止」看板で一旦56号線に出て進み、右に迂回する。
(道路工事が完成した時点で、ちょっと様子が変わるかもしれない。) |
 |
 |
 |
左手前方に、工事中の新しいトンネル。まだ、道路が必要なのかね~。
立入禁止区間を過ぎて、再度芳原川沿い歩道を進み、「津島大橋」バス停前を通る。 |
 |
 |
 |
その先の、岩松川にかかる津島大橋のところで右折し、坂道を下り岩松川沿いに進む。
アレ!アンパンマン? それとも、向こう横丁の美人?いずれにしても、可愛くて素敵です。 |
 |
 |
 |
分かれ道は、右手を進む。
なんとなくタイムスリップしたような町並み。
宿で聞いたことには、ここ岩松には、岩松町町並保存会があり、町並保存に熱心とのこと。
今日宿泊する三好旅館は、分かれ道からすぐのところの左側にあるが、荷物だけ預かったもらって先に進む。
右側に、大正期に病院として建築された江口邸。 |
 |
 |
 |
津島町商工会の階段脇に、へんろ休憩所。右側に、昭和4年醤油屋として洋風に建築された内山商店。
また右側に、岩松に残る最大規模の町家の1つの西村邸。 |
 |
 |
 |
規模が大きく、照明設備もあるきれいな公衆トイレとテーブルと椅子。
派手な看板の「てんやわんや文六餅」文六堂。ただ、ここでは、文六餅は買えず、果たしてどこで?
てんやわんや:昭和を代表する獅子文六が、
終戦直後妻の実家がある愛媛県宇和島市津島町(旧北宇和郡岩松町)に疎開していた時の様子を題材としてもので、
四国南西部のある村(若松町)の日本からの独立騒動を描いている。
左側に、町人長屋。 |
 |
 |
 |
右側に、臨江寺の昭和14年建立山門。
山門上部の櫓窓が、大正ロマンのつくりになっているとのこと。
町並みを出ると右側に、左方向を示す道標ワッパン2枚。 |
 |
 |
 |
←の方向を何度見ても、岩松川で遮断されていて何もなし。
後でわかったことであるが、5年年ほど前まではここに「岩松橋」がかかっていた。よくみると、対岸にその橋跡がある。
人騒がせでした。
平成22~23年に、新しい「岩松橋」を、数十m上流に作ったので、遍路道もそこを渡る。
道標ワッペンから右手にカーブして進み、岩松川にかかる「岩松橋」を渡る。 |
|
|
正面に郵便局(合成写真)が見える岩松橋を渡り、続いて遠近川にかかる花本橋を渡って右折し、56号線を進む。
今日は、ここまで。
ここは、観自在寺から、25.0km地点。
時は、16:07。観自在寺から、約8時間30分。 |
| |
| 今日の宿 |
|
 |
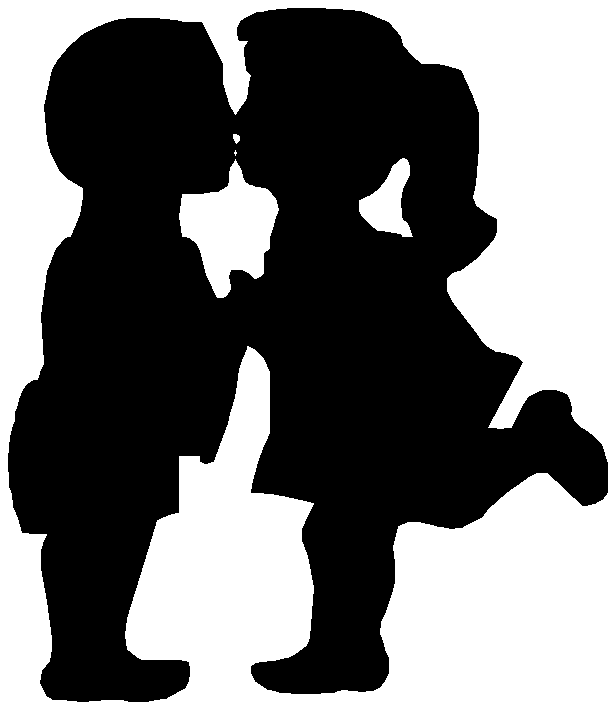 |
| 三好旅館(合成写真) (一泊2食付 7,000円) |
| 本館と別館(写真)があり、本館は食事、別館は宿泊。 |
| 別館は、130年前の建築で当初3階建だったのが、いつかの時点で現在の2階建てになったとのこと。(タマちゃん係員談) |
| 玄関両側に、男女一対の裸体カッパ像:「ダメよ、ダメダメ、そんなところでオシッコしては!」 |
| この日の宿泊客は、金沢市からの元山男の歩き遍路一人と私たち夫婦の計3人。 |
| 宿には、女将、何しろ賑やかなタマちゃん(女性)と食事係りの若い美人。 |
| ここは、何が何でも料理で、今まで宿泊したところでは1,2を争うほど美味で量的にも充実している。 |
| 食事は、本館食事室で3人一緒。 |
| 夕食;8皿+漬物+味噌汁。特筆は、鰻と伊勢海老料理が出ること。朝食:7皿+味噌汁。 |
| 朝食時に、女将さんがきれいな着物ときれいなお化粧して歓迎のご挨拶。すごい美人!(前夜は、料理に専念とのこと。) |
| お別れの挨拶ということで、女将さんの差し出す握手の手。 |
柔らかく温かくて艶めかしい手に触れた瞬間、まだまだ生身の男。思わずアタマクラクラ。
(女将さんの握手は、どの宿泊者ともしますので、誤解なく。) |
| 旅の友にと、各自リポビタンDを1個いただく。 |
























































































































































