|
|
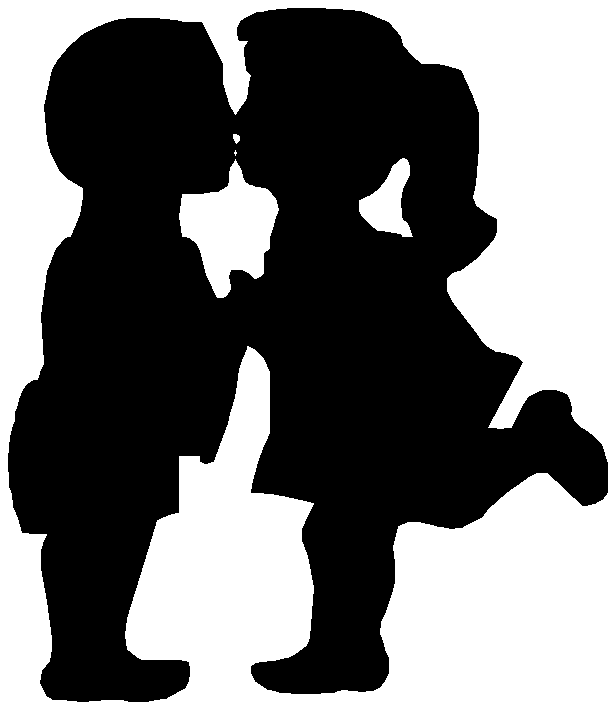 |
歩く 鎌倉街道・中道
新古河駅ー 鎌倉街道スタート地点
(埼玉県加須市向古河) (茨城県古河市) |
| iー愛ロマンチカ |
|
この区間は、2013.4.18に歩いた。
埼玉県加須市向古河の東武日光線新古河駅から、
スタート地点とした県道261号線の茨城県古河市中央町2丁目2の丁字路までの、
約2kmのいわゆる支道区間である。
この区間は、当時の古河城跡があるが、渡良瀬川改修工事で現在は殆ど消滅して跡形がない。
|
|
|
横浜を早朝出発し、相鉄線、JR東海道本線、都営浅草線、東武日光線を乗り継いで、
8:03埼玉県加須市向古河の東武日光線新古河駅に到着。
|
|
|
駅東口出口から東に向かい、渡良瀬川堤防の国道354号線に出て右折する。
すぐ先丁字路交差点を左折して、渡良瀬川にかかる三国橋を渡り、
途中埼玉県から茨城県古河市に入り三国橋信号交差点に出る。
支道は、354号線左側の2番目の細い道を進む。
橋を渡ると、その先渡良瀬川東河畔は広大な古河城の敷地であり、
三国橋周辺から渡良瀬川を渡し船で渡っていた。
古河城:平安時代末期頃下河辺行平が築いた城館が起源とされている。
室町時代には、古河公方・足利成氏が本拠とし、以後関東における中心の一つとなった。
江戸時代には、多くの譜代大名が入れ替わりで城主を務めた。
明治末に開始された渡良瀬川の改修工事で残された城跡も殆どが消滅している。
|
|
|
立寄り:三国橋信号から左折し堤防沿いに進む。
すぐ先分かれ道は右手を進み、
右側の「渡良瀬川治水紀功副碑」前から右折して細い坂道を下り、
下り切った右側に「史蹟 古河城船渡門址」碑が立つ。この辺一帯が渡し場であった。
|
|
|
道なりに進んで、右にカーブして下り、
すぐ左側に城主永井直勝の創建で、その墓のある永井寺。
その先の約60mの丁字路を右折した右側に、
保元・平治の乱で活躍しその後宇治川の戦いで敗れて自殺した、
源三位頼政の首が葬ってあるという頼政神社。
元は古河城北端にあったが、1912年(大正元)渡良瀬川改修工事で現在地に移されたもの。
|
|
|
元の三国橋信号に戻り、国道354号線の左側の2本目の細い道を進む。
すぐ階段を下りて右折し、354号線高架沿いに進む。
|
|
|
その先の分かれ道は、左手を道なりに進み、閑静な住宅街の中を通り、
分かれ道から約300m地点で信号交差点に出る。
支道は、直進する。
|
|
|
立寄り:古河城跡に立ち寄るため、信号から右折し古河第一小学校西門前を通り、
約300mの「古河歴史博物館文学館」看板のところから左折してタイル道を進む。
約100m先左側の「歴史博物館」と庭園のあるところが、古河城出城諏訪郭跡。
道を挟んで反対右側に、鷹見泉石記念館。
|
|
|
元の信号に戻り、
直進してゆるい坂を上り右側古河第一小学校前の一角に「鷹見泉石生誕之地」碑。
鷹見泉石:江戸時代、古河藩の家老でかつ蘭学者であった。
十郎左衛門忠常といい、泉石は引退後の号。
東京国立博物館蔵の渡辺崋山の描いた「鷹見泉石像」は近世画の傑作として、
国宝に指定されている。
さらに道なりに200mほど進み、石畳の道になり両側に当時の姿を思わせる建物が続く。
|
|
|
右側に、
古河城文庫蔵を移築した土蔵造2階建「坂長」店舗と古河城乾燥蔵を移築した「お休み処」。
その先「肴町米銀」左側に隣接して「史蹟古河藩使者取次跡」碑。
|
|
|
石畳道の突当りの丁字路が、
スタート地点古河市中央町2丁目2の鎌倉街道・中道の県道261号線。 |
| |
|
|
| |
| |
| |