|
 |
|
長尾寺仁王門出発、7:38。
参道から、あづまや旅館前の車道に出て左折する。 |
|
|
| すぐ先の「旅館やなぎ屋」角を右折し、さぬき市長尾西地内の道を進み信号交差点で長尾街道を横断する。 |
 |
 |
 |
| 道なりに進み、次の信号交差点で県道10号線さぬき東街道を横断して、この時間全く人も車も通らない道を進む。 |
 |
 |
 |
宗林寺前を通り、自転車に乗る女子学生の信号を直進し、右側に赤い幟。
奥に、石の弘法大師座像を本尊とする川原の庵・寶政寺。 |
 |
 |
 |
その先で鴨部川にかかる塚原橋を渡り、続いて県道3号線の塚原信号交差点に出る。
実は、ここで間違い信号を直進してしまい、結局23分のロスタイム。
正解は、3号線を左斜めに横断して、 |
 |
 |
 |
| 反対側の細い道に入りる。常夜灯の立つ道を進み、右側に石像の釈迦像を祀る釈迦堂。 |
 |
 |
 |
その先の右側の小さな広場の奥に、1764年(明和元)印誉意心法師草創で本尊阿弥陀如来の一心庵。
道なりに進み、左側に「おへんろさん休憩所」。 |
 |
 |
 |
ゆるい坂道となり、道の左下にトイレ、右側に高地蔵。
高地蔵:ここは、旧長尾西、長尾名、前山村の3ヵ村の村境であったところで、
1861年(文久元)に3ヵ村の庄屋が発起人となって高さ4m余の台座の上に座った地蔵を建立した。 |
 |
 |
 |
同じ敷地に、志度・長尾から中津まで馬車が通っていたころの曳き馬を弔った「馬の墓」。
さぬき市前山地内に入り、坂道を上り切って県道3号線と合流してゆるい坂を上り、
市乃江バス停先の分かれ道は、3号線と別れ左手を進む。 |
 |
 |
 |
川沿いの道を進み、道端に野仏像が立並ぶ先の蔵のような建物は「出土品保存庫」。
発掘作業をしているのだろうか?もしかしたら、これら野仏像も?
住宅地の中の坂道を上る。 |
 |
 |
 |
| その先で車道を横断して反対側の道に入り、突当りで県道3号線と再度合流して、梅ヶ畑バス停前を通りゆるい坂道を上る。 |
 |
 |
 |
| 左側に、「↑700m 前山おへんろ交流サロン」看板。橋を渡り、左斜め前方に前山ダム。この円板は、休憩所。 |
 |
 |
 |
「へんろ資料館 ↑500m」看板。資料館は、おへんろ交流サロンと同じところにある。
ここから、下り坂となり、左下に前山ダム湖。3号線をひたすら下り続け、左にカーブする。 |
|
 |
|
カーブするコーナーで、「旧へんろ道 大窪道入口(丁石道を歩こう)」看板から右折する。
ただ、ここでは、この先数十mのところある「おへんろ交流サロン」に立寄ってから、戻ってくることにする。
時刻は、9:17。長尾寺出発から、約1時間45分。(道に迷った、23分のロスタイムを含む) |
| おへんろ交流さろん |
 |
 |
 |
そのまま左にカーブし、左側に「前山おへんろ 交流サロン」立看板。
駐車場奥の、「前山地区活性化センター」内に交流サロンと資料展示室。。
館内には、親切な美人係員が一人。
すぐ、お茶とお菓子を出していただきました。ありがとうございました。また無料のミカンの山もありました。
住所氏名を記入して、「四国八十八カ所遍路大使任命書」書状を頂きました。(無料)
書には、通し番号が記入されていて、妻が第100X号、私が第100X号」。これって、今年の訪問客の数?
ちなみに係員にお尋ねしたら、遍路客は一日平均15名、年間で約2500人(昨年は1200年記念で3500人)とのこと
数字が合わないような気がするが、詮索なし。
きれいな水洗トイレがあります。 |
| |
 |
 |
 |
先ほどのコーナーの分かれ道に戻る。時間、9:45。交流サロンでの休憩時間は、約20分。
「旧へんろ道」看板から花折山へんろ道スタート。看板の脇に、「さぬき市建設残土処分場」看板があり、同じ→方向。
右に左に蛇行して坂道を上り、しばらくすると正面の○印に山道へ導く道標があるが、これは新道の遍路道。
旧へんろ道は、舗装道を上り続ける。 |
 |
 |
 |
所々に、「待避場所」看板。これは先ほどの「建設残土」を処分場まで運搬するトラックがすれちがいのため待避するところ
ちなみに、1番から始まり、10番まである。
そーら、さっそくトラックがやってきました。不思議なのは、来るときはいつも数台繋がってくるのです。
左側に、自然石でできた「丁石」
案内板によると、丁石に刻まれている文字は次の通り。
「施主 井戸村成瀬兵太 是より於くぼ迄二里 願主 与洲徳右ヱ門」
この徳右ヱ門は、寛政から文化年間にかけてへんろ道の整備に尽力し、多くの道標を建立した人、とある。 |
 |
 |
 |
| 蛇行して上り、時には下り、「待避場所10」を過ぎる。 |
 |
 |
 |
何故か道路は汚れて正面に残土処分所。処分場前を左折して塀沿いに進み、「花折山へんろ道 出口全長2.0km」看板。
出口がどこか不明であるが、要するにあと2kmくらい歩けばよい、ということのよう。17 |
 |
 |
 |
下り道は楽で、左側に休憩所。
多和相草東地内に入り、東花折峠あるいは相草東峠ともいう坂道を下り左側に、「七十丁の地蔵」。
大窪寺は、この地蔵から約7.6km。
なお、大窪寺の丁石は、1762年(宝暦12)5月から3年間で七十丁石まで作られたという。 |
 |
 |
 |
こんなところに人家と思ったが、既に空き家でした。
ちょっと急になった坂道を下り、ようやく見えた人家の先で左にカーブする。 |
 |
 |
 |
左側に道の辻六十六丁石で、大窪寺まで約7.2km。
左にカーブしその先で右からの道と合流して進み、突当りで県道3号線に出て右折し、多和相草西地内に入る。
県道3号線との合流点が、10:46。 長尾寺から8.6km、所要時間約3時間。 |
 |
 |
 |
額峠バス停前を通り3号線の坂道を下って多和額西地内に入り、
延々と下り坂は続き、分かれ道に「←重要文化財細川家住宅」看板。
立寄るため、左手の坂を下りてしばらく探したが、道案内もなく結局細川住宅に辿りつけなかった。
もとに戻り、3号線の坂を下る。21 |
 |
 |
 |
| 多和助光西地内に入り集落の中を通り、多和駐在所前信号丁字路を右折し、多和橋を渡り県道377号線を進む。 |
 |
 |
 |
さぬき市役所多和出張所脇を通り、
多和東谷地内に入り左側に、「東谷庚申塔(青面金剛)」像と弘法大師が一夜の庵を結んだという「一夜庵」案内板。
377号線は、延々と上り坂となる。
この辺りで、歩いておられた中年の女性から干し柿を2連いただく。お接待でした。
とても珍しいもの、ありがとうございました。 |
 |
 |
 |
長い上り坂の頂上あたりに、現在は移転しているが「雲の峰三十四丁石」があった。
多和竹屋敷地内に入り377号線は下り坂となり、
左側に「おへんろみち休憩所」とその手前草むらに竹屋敷口三十丁石。大窪寺まであと、約3.3km。 |
 |
 |
 |
多和槙川地内に入り、平坦な道を左にカーブし、
その先の分かれ道は、377号線と分かれ左手に入る。分かれ道の少し離れた右手に、花が供えれている「国境の二十一丁石」 |
 |
 |
 |
左手ののどかな一本道をしばらく進み、
多和兼割地区内に入り、林の手前から右折し「十四丁石」道標の立つ草むらの坂を下り、左折して石橋を渡る。 |
 |
 |
 |
| 道標なしで人の通った形跡のない、すごい草むらの中を勘を頼りに進み、根拠もなく廃側溝を頼りに右にカーブする。 |
 |
 |
 |
「十四丁石」道標。方角は間違っていなかったと確信し←方向へ進み、
次の「十四丁石」道標の矢印は左手下方を示していたが、あまりにもひどい状態なのでご遠慮申し上げ、
十四丁石などどうでもよくなり、、道の形がある右手の坂を上る。
山を上り切ったところに、なんと!こんなところに門扉と道標ワッペン。
へんろ道に間違いないとわかったが、何故門扉?
疑問があったが、扉が開いていたので門を通る。 |
 |
 |
 |
坂を下り、道路の擁壁の下を進み、突当りでコンクリート坂を上ると、正面に民家。
道標もないので、必然的に民家の前の木立の中を通る。 |
 |
 |
 |
恐るおそる、キョロキョロしながら道標を探しながら民家の前を通り外れまで行き、
ようやく藪の中に1枚の道標ワッペンを発見。
ただ、針金で木の枝から吊るされているので、風が吹くたびくるくる向きが変わる。どっちに行けばよいのやら…・。
意を決して直進し田を傷めないように端をそろりそろりと歩く。 |
|
 |
|
突当りに、ここにも門扉と道標ワッペン。
ただ、ここの門扉は閉められていてしっかり固定されている。
前方には、もう一枚のワッペンが見え、右手には民家。ただ、道らしい道はない。
結局、不法侵入を避けるため、ワッペンの藪まで戻り、民家の脇を通り先ほどの車道に出て右折する。
難問
車道から脇道に入るこのへんろ道には、次の問題がある。 |
| ・初めの草むらには道も道標もないので、草木が繁茂するシーズンは困難を伴う。 |
| ・門扉があるところからは明らかに私有地。道標はあったが、果たして通行が認められているのかどうか。 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
車道に戻り、坂道を上る。その先で右手から合流する道(○)が、先ほどの門扉で諦めたへんろ道。
道なりに進み突当り丁字路を右折する。 |
 |
 |
 |
道が開け、ガードレールに「大窪寺まで0.7km」道標。
道なりに進み、前方に大窪寺の堂宇が見えてくる。 |
|
|
| 坂道を下り、分かれ道は左手の仁王門への参道を上る。本堂前にて。 |
| 大窪寺到着、12時50分。 |
| 長尾寺から、14.1km、所要時間 約5時間。(道に迷ったロスタイムと交流センター休憩時間を含む) |
| |
| 第88番札所医王山大窪寺 (おおくぼじ) (香川県多和兼割) |
| 開基:行基 本尊:薬師如来 |
| 標高787mの矢筈山の山腹に建ち、古くから女性の参拝が許されていたため「女人高野」とも呼ばれている。 |
| 717年(養老元)に行基により開かれ、その後唐から帰国した弘法大師が堂宇を建て薬師如来を刻み本尊とした。 |
| 天正年間(1573~92)に、長宗我部元親軍の兵火で堂宇、仏像、経典が殆ど焼失した。 |
江戸時代に堂宇は再建されたが、1900年(明治33)の火災で二天門を残し堂宇は焼失した。
現在の諸堂はそれ以降再建されたもの。 |
| 宝杖塔には、旅を終えた金剛杖を有料で奉納することができる。 |
 |
 |
 |
| 高さ13.5m仁王門 |
本堂 |
不動明王 |
 |
 |
 |
| 真魚(弘法大師の幼名)像 |
宝杖塔 |
二天門 |
| |
参拝を終えてから、二天門から参道階段を下りて、八十八庵店でさぬきうどんを食する。
あづまや旅館からもらった地図を差し出したら、土産を一品いただきました。ありがとうございました。 |
店のすぐ近くのバス停から、13:30発コミュニティバスに乗り長尾の大川バス停で降りて、
琴平電鉄長尾駅から琴平電鉄栗林公園駅へ。 |
| 栗林公園を17:00閉園時間まで約2時間、無料ボランテァガイドの案内で楽しみました。 |
|
 |
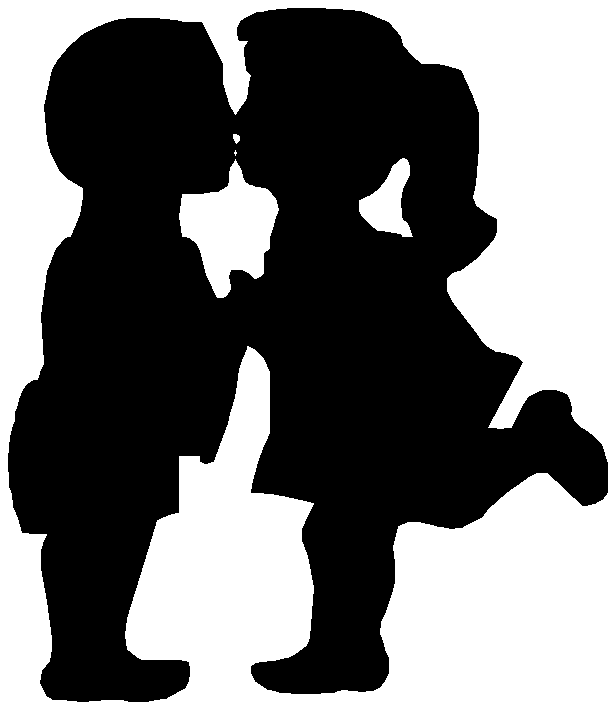 |
|
琴平電鉄長尾駅 |
|












































































































